「体の悩み@ビタミン・栄養2」では、症状別に効果的な「ビタミン・栄養」を詳細に紹介しています。
今、あなたに必要なビタミン・栄養は...
肩こり

肩こりはデスクワークなど長時間同じ姿勢でいて、肩の筋肉が緊張した状態が続くと起こりやすくなってきます。
緊張により、血行不良となり筋肉の疲労物質である、乳酸・ピルビン酸が溜まるのが直接の原因といわれています。
軽度の肩こりはビタミンを摂り、肩の軽い運動で血行が良くなり改善されますが、長引くようであれば、適度に重いダンベルなどを使い、定期的に適度な運動を心掛けましょう。
1・2kgのダンベルなどを両手に持ち、頭の上での上げ下ろしを最初は無理ない程度に(10~20回)3セット程を毎日又は1日おきに行うことで、血行も良くなり筋力アップにもつながります。
しかし、酷い肩こり更に腕や手にしびれを感じるときには、ビタミン・運動不足ではなく、他の病気であることも考えられるため、専門医の検査を受けましょう。特に、しびれ等がある場合は、首などの神経圧迫により起こることが多いようです。

むくみ

体内の水分バランスが崩れてしまい、通常は排出されるはずの水分が溜まってしまうことでむくみが起きてしまいます。主に、手・足・顔に現われ、水分により皮膚の弾力性がなくなります。
通常、この両栄養素がバランスよく保たれていますが、カリウム不足が起き、ナトリウムが多くなることにより、細胞の外部に余分な水分が溜まってしまうのです。
むくみとして内蔵の病気も考えられますが、病気が原因でない場合は、ナトリウムを控えてカリウムが多い食事で改善できます。また、適度な運度・マッサージにより血液の循環を良くするとで、水分の排出が良くなります。特に下半身は、血行不良が起きやすいため、ウォーキング・軽めのジョキングなどが、むくみ解消に効果的です。

- 「ナトリウム(塩分)・カリウム」が、効果的
ナトリウムは、カリウムと共に体の細胞の水分調整をする働きがありますが、摂りすぎると水分バランスが崩れ、細胞に余分な水分が貯まり、むくみが起きてしまいます。日常でも少しの油断で、高塩分の食べ物を摂ってしまうことも多いです。
- 味噌汁1杯(塩分 ≒ 1.5g)
- しょうゆ大さじ2杯18g(塩分 ≒ 6g)が目安です。
カリウムは、体内のナトリウムが過剰になると、排出する働きがあり、むくみ解消には効果的な栄養素です。カリウムを十分に摂ることで、ナトリウムとカリウムのバランスの調整及び、血圧を正常に保つ効果があります。(高血圧予防)
多く含まれている食品として、「昆布・大豆・アボガド・さつま芋・バナナ・キウイ」などです。これらの食品は、加熱調理するとカリウムの損失が大きくなります。過剰摂取による悪影響はありませんが、肝臓にトラブルがあるときの摂取量には注意が必要です。
しみ・そばかす

しみ・そばかすは、皮膚のチロシンという物質が刺激を受けメラニンになり、皮膚に残った状態をいいます。
中でも、紫外線による日焼けが、一番多いようです。肌は長時間、紫外線を浴びてしまうとメラニン色素により肌が黒くなり、更に活性酸素が作られます。
この活性酸素は、健康な肌を酸化させ老化を早め「しみ・そばかす・しわ」の原因になってしまいます。紫外線対策は、外出時に日焼け止めクリームを、しっかり塗ることですが、それでも日焼けした場合、「ケア用の化粧品・美白効果と抗酸化作用があるビタミンC」などをを併用することにより「しみ・そばかす」を抑えることができます。
ちなみに紫外線を浴びることにより、体内でビタミンDが合成され、骨が丈夫になるというメリットがありますが、あくまでも適度な日光浴と考えたほうがよいです...

- 「ビタミンC・A・E」が、効果的
ビタミンCは、肌のハリを保つコラーゲンを作り、更に美白効果があります。また、ストレス及び紫外線でできる活性酸素を抑制する効果があるので「しみ・そばかす」の減少に期待ができます。多く含まれている食品として「アセロラ・キウイ・ピーマン・イチゴ・グレープフルーツ」などです。
皮膚や粘膜の新陳代謝を活発にし、免疫機能を高めてくれます。これにより皮膚や粘膜を若々しく健康に保つと共に「細菌・ウイルス」の外部侵入を防いでくれます。ビタミンAは、多く含まれている食品として「鶏レバー・豚レバー・うなぎの蒲焼き・ナチュラルチーズ」などです。
同ビタミンは、ビタミンCと共に活性酸素による肌の老化を防ぎ(抗酸化作用)「しみ・そばかす・かすみ」を改善してくれます。「若返りのビタミン」とも呼ばれ、多く含まれている食品として「アーモンド・ナッツ・かぼちゃ・うなぎの蒲焼き」などです。
下痢

下痢は、腸で吸収できる水分の限度量を超えた場合に起きます。通常、1日に約9~11?程の水分が腸に送られ、その内の8割が小腸で吸収、残りの水分が大腸で吸収されます。
しかし、水分を多く摂りすぎることにより限度を超えてしまい、下痢便になってしまいます。原因としては「水分の過剰摂取・食べ過ぎ」などが多いですが、それ以外にも「ストレス・食物アレルギー・ポリープ・癌・大腸炎」などがあります。
注意点として...「下痢⇔便秘」が交互におきて腹痛を感じたり、血便の時は下痢ではない症状が考えられるため、早期に検査してもらいましょう。下痢の後、更に水分を摂るのは症状を悪化させてしまうと思われますが、これは逆効果であり下痢により水分が多く排出され脱水状態になっているので、適度な水分補給は欠かせません。
また、水分と一緒にミネラルも排出されているため「麦茶・ミネラルウォーター・スポーツドリンク」などを飲むとよいでしょう。以降「コーヒー・牛乳・ビール・ダイエット甘味料」などは、下痢の再発になりやすいため、しばらくは症状が良くなるまで控えたほうがよいです。

- 「乳酸菌(ビフィズス菌)・オリゴ糖」が、効果的
人間の腸にはいろいろな細菌がすんでいますが代表的なのが乳酸菌で、この乳酸菌にもいくつか種類があり、よく知られているのが、ビフィズス菌です。
乳酸菌は善玉菌であり便通を良くし、更に腸での抗生物質の副作用を抑えるなど、腸内環境を調整してくれる働きがあります。乳酸菌は便秘以外に下痢になったときも、効果的な栄養素です。乳酸菌が多い食品としては、ヨーグルトが一番良いでしょう。
オリゴ糖は糖分の仲間で、胃・腸で吸収されにくいため、ダイエット用の甘味料としても使われています。この栄養素はビフィズス菌のエサになるため、ビフィズス菌を増やす働きがあります。これにより、腸内環境を良くし働きを整えるので、下痢にも効果的です。
オリゴ糖は人により症状が重くなるケースがあるため、様子を伺いながらの摂取を心がけましょう。
ダイエット

「食べ過ぎ・運動不足」これによる太りは、生活習慣病のリスクが高まります。肥満の人の健康維持には「ダイエット=適度な体重に落とす」これには、脂質・糖質を減らし、ビタミンB1・B2・ミネラルを十分摂り適度な運動も欠かせません。
大きなウエイトをしめるのはやはり食事ですが、ポイントをいくつかあげてみます。
- 栄養・ビタミンのバランス
低カロリーの「野菜・キノコ類・海草・こんにゃく」などを多く取り入れることにより栄養バランスだけでなく食物繊維も摂りいれることができるため、便秘予防にも効果的です。
- 食事時間
規則正しい食事時間により、太りにくいことが知られています。更に、約25分~35分かけたゆっくりな食事により、脳の満腹中枢が働き、食べ過ぎを抑える効果があります。

- 「脂質・糖質・ビタミン・ミネラル全般」が、効果的
ダイエット=脂質をいかに少なくする。肥満の原因として、食べ物からの脂質・糖質が多すぎて、体内に脂肪として貯えられるからです。脂質は「1g → 約9kcal」ダイエットには大敵です。脂質は「肉類・揚げ物・炒め物」などに多いためダイエットを考えているなら、食生活から見直すことが必要です。
糖質は体のエネルギー源のため不足すると、だるさ・疲労感が起こります。特に、脳細胞及び赤血球のエネルギー源は、糖質(ブドウ糖)なので、極端なダイエットにより糖質を摂らないのは、危険でもあります。
糖質は脂質に比べ「1g → 約4kcal」と少ないため、多少摂りすぎてもダイエットへの影響は小さいようです。とはいえ、摂り過ぎにより体内で消費できなかった場合、、脂肪に変わってしまうので気をつけたいものです。多く含まれる食品として、「ご飯・麺類・芋類・果物」などなので食べ過ぎには注意しましょう。
- ビタミンB1... 糖質(炭水化物)をエネルギーに変える働きがあります。糖質を多く摂る人は、不足しないよう心がけましょう。
- ビタミンB2... 脂質をエネルギーに変える働きがあります。脂質を多く摂る人には同ビタミンが効果的です。
ダイエットにより、食べ物の量や種類を減らしてしまうため、いろいろな栄養素が不足してしまいます。特にビタミン・ミネラル不足になりがちなので、低カロリーの野菜や、「マルチビタミン・マルチミネラル」のようなサプリメントで補うとよいでしょう。
標準体重を知るにはどうすればいい?
ダイエット = 目標とする体重 (標準体重)
標準体重の計算方法としてはいくつかありますが、多く使われる「BMI」という方法を記してみます。
体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) = BMI
- 体重82.5kg・身長170cmの人の場合 ... 82.5÷1.7÷1.7=28.5 (肥満度1)
- 体重92.0kg・身長160cmの人の場合 ... 92.0÷1.6÷1.6=35.9 (肥満度3)
計算したBMIの数値により下表参照。痩身~肥満 (肥満度1~4) に分けられています。
身長から理想的な体重を知りたいときには?
身長(m) × 身長(m) × 22 = 理想体重
- 身長165cmの人では ... 1.65×1.65×22=59.9kg
- 身長175cmの人では ... 1.75×1.75×22=67.4kg
| BMI | ||
| 痩身 | 18.5未満 | |
| 普通体重 | 18.5以上 ~ 25.0未満 BMI 22が理想的な体重とされています。 |
|
| 肥満 | 肥満度1 | 25以上 ~ 30未満 |
| 肥満度2 | 30以上 ~ 35未満 | |
| 肥満度3 | 35以上 ~ 40未満 | |
| 肥満度4 | 40以上 ~ | |

- 悪酔い・二日酔い
飲酒により血液中のアルコール濃度が高くなりますが、これを分解し体に害がないようにするのが肝臓の働きです。
このとき肝臓ではアルコールが分解される量に比例して、ナイアシン(ビタミンB群)も消費されます。
二日酔いは、この過程で「アセトアルデヒド」という有害物質が多くできすぎてしまい、肝臓で処理しきれなくなり残ってしまうことにより起こります。悪酔い・二日酔いを避けるには、「豆類・肉類・魚介類」などをつまみながら飲むのがよいです。
「枝豆・酢の物・豆腐」などには、ナイアシン(ビタミンB群)・たんぱく質が多く含まれているので、理にかなった食べ物といえます。また、少し飲みすぎを感じたときには飲酒の後に、コーヒー・日本茶(タンニンが含まれている)や、カリウム・果糖が含まれている果物を食べることで、二日酔いを防ぐことができるようです。

-
-
- 「ナイアシン (ビタミンB群)・ビタミンB1・たんぱく質」 が、効果的
-
飲酒によりアルコールは肝臓で分解されます。このとき消費されるのがナイアシン(ビタミンB群の1つ)です。 ナイアシン不足や、飲酒の量が多いとアルコールの分解が追いつかないため「吐き気・おう吐」などの悪酔いが起きてしまいます。
同栄養素は、広く食品に含まれ体内でも合成されるため、ナイアシンの不足はあまりありませんが、飲酒を多く感じるときには気をつけて補給したいものです。
アルコールの分解がナイアシンで追いつかなくなると、ビタミンB1も分解のために消費されます。長期的に過剰な飲酒を続けてしまうと、ウェルニッケ脳症(ビタミンB1の欠乏症)になる場合もあります。
「豆類・魚介類・肉類」などに多く含まれる栄養素で、アミノ酸に分解されて吸収されます。このアミノ酸の1つの物質に「トリプトファン」があります。これは体内でアルコールを分解する、ナイアシン(ビタミンB群)に合成されます。
タバコの煙は「ニコチン・タール・一酸化炭素」などの有害物質を含んでいるため「癌・動脈硬化・心臓病・COPD」などの発生リスクが高くなります。

ある検査では、タバコ1本あたりビタミンCが25mg消費されるという結果がでています。成人に必要なビタミンCの摂取量は、「1日=100mg」です。しかし、喫煙者がタバコを4本吸うことにより、1日に必要なビタミンC全てが消費されるということです。(少し驚くような数値です)当然、体内に貯えられているビタミンCもありますが、喫煙者にとっては十分な量とはいえません。
健康を考えると禁煙が良いのですが、できない人はビタミンCが多く含まれる「アセロラ・キウイ・イチゴ・レモン」及び、ビタミンEが多く含まれる「アーモンド・ナッツ類・モロヘイヤ」などを十分摂るように心がけましょう。ヘビースモーカーの人は、食品からの摂取量は限られてしまいますので、「サプリメント・健康食品」などで摂取すると効果的です。

- 「ビタミンC・E」が、効果的
タバコを吸うことにより、ニコチンなどの有害物質が体内に侵入してきます。ビタミンCは、これらを排出するため大量に消費されます。ビタミンC不足になると有害物質が体に貯まり、「癌・動脈硬化」など様々な病気をひき起こしてしまいます。
ビタミンCは、喫煙時にできる活性酸素を分解し、体の老化を防ぐと共に白血球(免疫力)の働きを高め、病気への抵抗力をつけてくれます。
ビタミンEはビタミンCと同様、活性酸素を抑制する抗酸化作用があり、喫煙による悪影響を防ぐ働きがあります。この抗酸化作用により体の酸化(老化進行)が少なくなり、血管や細胞の機能が保たれることで血行促進及び生活習慣病などの予防につながります。
体の悩みに効果的(ビタミン・栄養素)1については、コチラへ。
病気の症状別効果的(ビタミン・栄養素)1については、コチラへ。
病気の症状別効果的(ビタミン・栄養素)2については、コチラへ。
体の疲れ回復法については、コチラへ。
心・ストレスからの回復法については、コチラへ。

ビタミンの詳細(種類・働き・性質)については、コチラへ。
ミネラル・食物繊維については、コチラへ。

3大栄養素「食品名・含有量一覧表」については、コチラへ。
食からの疲労回復については、コチラへ。
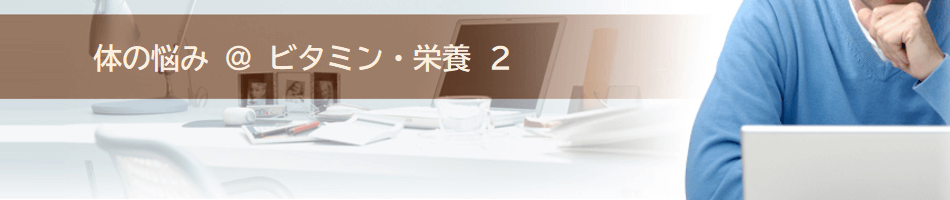
糖質(炭水化物)から、エネルギーを作る働きがある栄養素で、筋肉疲労の回復・肩こり予防・肩こり解消に効果が期待できます。更に、体のだるさ・疲労感の解消にも効果があります。ビタミンB1は、多く含まれている食品として、「牛豚肉類・大豆・そら豆・えんどう豆などの豆類」です。
活性酸素による血管の酸化(老化)を防ぎ、血行を良くする効果があります。このため、肩こりの原因である血行不良を、改善する効果があります。多く含まれている食品として、「アーモンド・ヘーゼルナッツ・ヒマワリ油・うなぎの蒲焼き・かぼちゃ・モロヘイヤ」などです。
ビタミンEと同様、血行促進の効果があり、肩こりの解消に役立ちます。「イチョウ葉エキス=イチョウの葉を乾燥させ、アルコールを使い成分を抽出したもの」最近では手軽にサプリメントが、通販・ドラッグストアで購入できます。